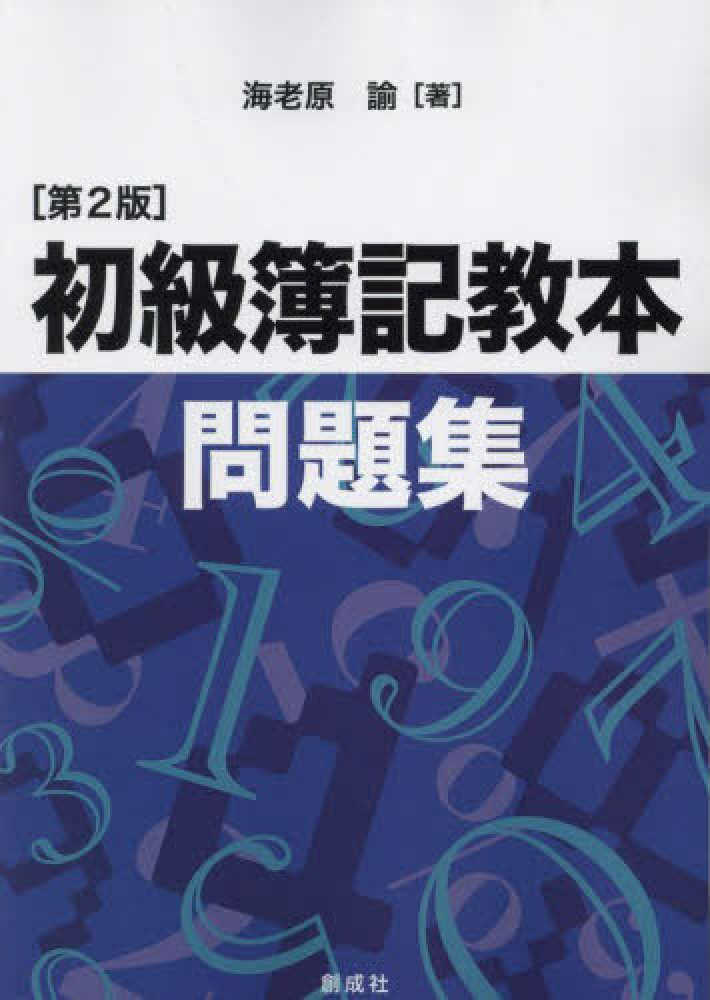給料
最終更新日:2024年06月15日
従業員に対して給料を支給するにあたっては、社会保険料(年金保険料・健康保険料・介護保険料・労働保険料)や従業員の給料に係る所得税・住民税をその支給すべき給料の額から天引きする必要があります(源泉徴収・特別徴収)。わが国では、社会保険料や税金の納付を、給料の支給を受ける従業員(労働者)ではなく、その従業員を雇用した企業に代行させる仕組みが採用されています。これは、いったん給料として支給してしまってから納税させるよりも、給料として支給する前に天引きしてしまった方が、確実に納付されるという制作的判断によるものといわれています。
給料からの天引き
社会保険料(年金保険料・健康保険料・介護保険料・労働保険料)
社会保険料の額は、給料の支給額(天引き前の金額)に一定の割合を掛けて求められます。ただし、この金額は従業員とその従業員を雇っている企業とで折半して負担することとなっているため、従業員の給料から天引きすべき金額は、当初の計算式で求めた金額の約半分となります(労働保険料のうち労災保険料は企業側の全額負担、雇用保険料は業種ごとに定められた一定割合で負担となっているため、ぴったり半額にはなりません)。
社会保険料の納付は、従業員に対して給料を支給する前に行う場合(前納)と、従業員に対して給料を支給した後に行う場合(後納)の2つのパターンがあります。前納する場合は、先に企業が納付すべき金額を立て替えておいて、後で給料から取り返すという形になります。一方、後納する場合は、先に給料から天引きし、預かっておいたものを後から納付するという形になります。
簿記上、社会保険料の記録は、従業員が負担するか企業が負担するか、前納か後納かによって、次のように、それぞれ別々の勘定を使って行います。
- 従業員負担のもの
- 給料日前に納めるもの……従業員立替金
- 給料日後に納めるもの……社会保険料預り金
- 企業負担のもの ……法定福利費
税(所得税・住民税)
従業員が負担する所得税(国に対して納付するもの)の額は、従業員ごとに「所得税の源泉徴収税額表」を使って求めます。また、従業員が負担する住民税(従業員が居住する都道府県、市町村等に対して納付するもの)の額は、各従業員が居住している市町村等から送付される「住民税課税決定通知書」に記載されている金額を使います。
どちらの税についても、従業員の給料から天引きした後、その翌月10日までに納付することが原則になります。社会保険料のように給料日に先立って企業が立て替えるということはありません。
簿記上、従業員が負担する所得税・住民税の記録は、それぞれ次の勘定を使って行います。
- 所得税……所得税預り金
- 住民税……住民税預り金
設例による解説
社会保険料の前納
従業員の給料から天引きする社会保険料(1年分)のうち前納分21,600円を当社の負担額23,400円とあわせて現金で納付した。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 従業員立替金 | 21,600 | 現金 | 45,000 |
| 法定福利費 | 23,400 |
従業員が納めるべき社会保険料の額を給料日前に納付した場合は、企業が従業員の代わりに立て替えたことになりますから、従業員立替金勘定を使って記録します。従業員立替金勘定は資産の勘定であり、後日、給料から天引きをしたときにこの勘定に記録した金額を消していきます。
給料からの天引き・給料の支給
従業員の給料300,000円から従業員が負担すべき社会保険料(うち前納分1,800円、後納分45,210円)ならびに所得税6,640円および住民税12,100円を差し引いた残額を普通預金口座から振り込んだ。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 給料 | 300,000 | 従業員立替金 | 1,800 |
| 社会保険料預り金 | 45,210 | ||
| 所得税預り金 | 6,640 | ||
| 住民税預り金 | 12,100 | ||
| 普通預金 | 234,250 |
給料日後に納付する社会保険料、税金については、預り金として処理します。これは、従業員が納付すべきこれらの金額を、納付のタイミングまで企業が一時的に預かっているという意味です。預り金勘定は負債の勘定であり、将来、社会保険料、税金を納付したときにこれらの勘定に記録した金額を消していきます。
なお、従業員の立場から、社会保険料や税を天引きする前の金額を月収(1年分の合計額は年収)、天引きした後の金額を手取金額といいます。上の例では、月収300,000円、手取金額234,250円となります。
所得税・住民税の納付
従業員の給料から天引きした所得税6,640円、住民税12,100円を現金で納付した。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 所得税預り金 | 6,640 | 現金 | 18,740 |
| 住民税預り金 | 12,100 |
所得税、住民税は、従業員の給料から天引きした金額をそのまま納付します。社会保険料のように企業の負担額はありません。どちらも、原則として、給料日の属する月の翌月10日までに納付する必要があります。
社会保険料の後納
従業員の給料から天引きした社会保険料のうち後納分45,210円を当社の負担額45,210円とあわせて現金で納付した。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 社会保険料預り金 | 45,210 | 現金 | 90,420 |
| 法定福利費 | 45,210 |
給料日後に社会保険料を納付する場合の仕訳は、給料日前に社会保険料を納付する場合の仕訳とほとんど同じですが、使用する勘定が従業員立替金勘定から社会保険料預り金勘定に変わります。納付は、企業が負担すべき金額(法定福利費)とあわせて行います。